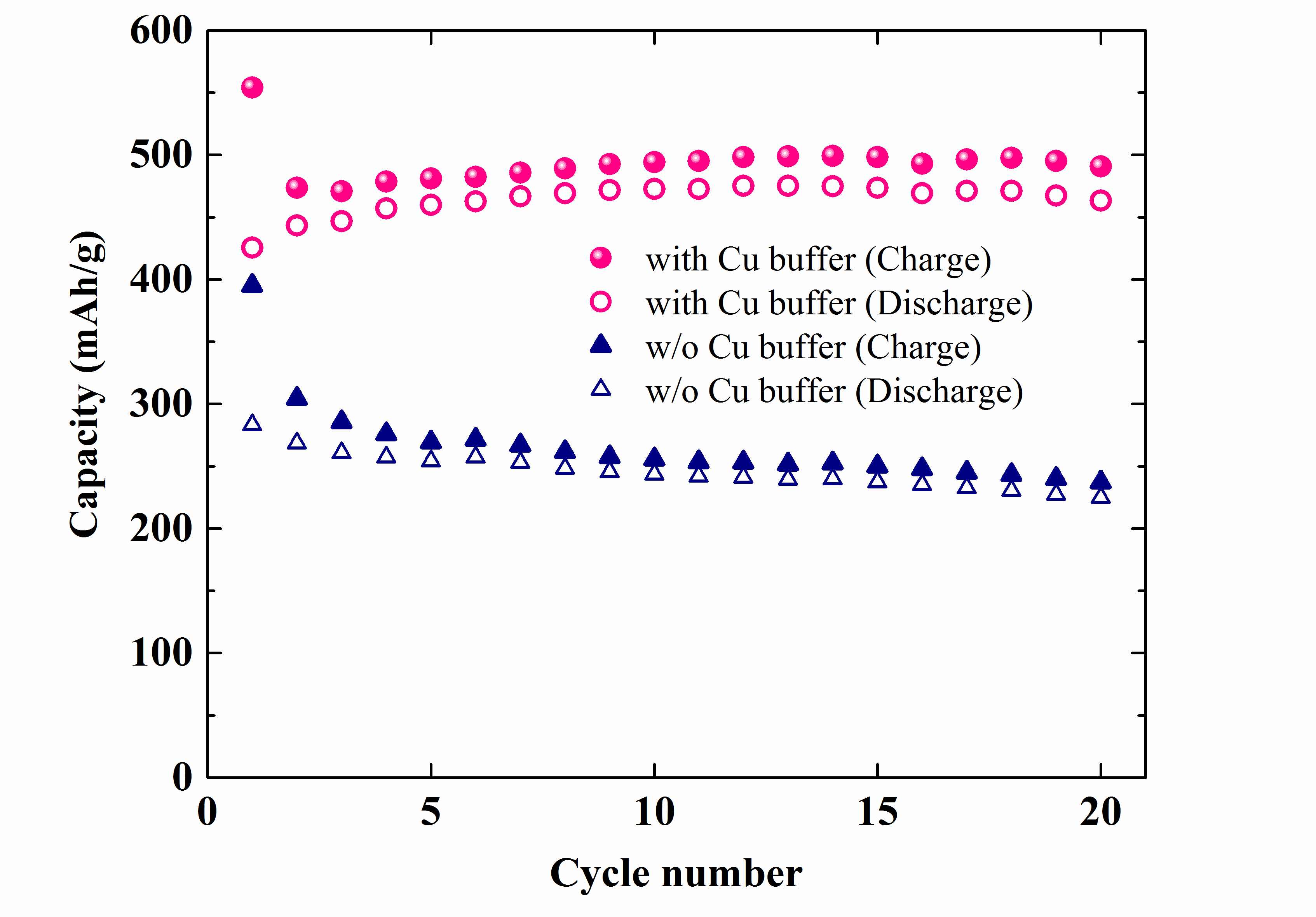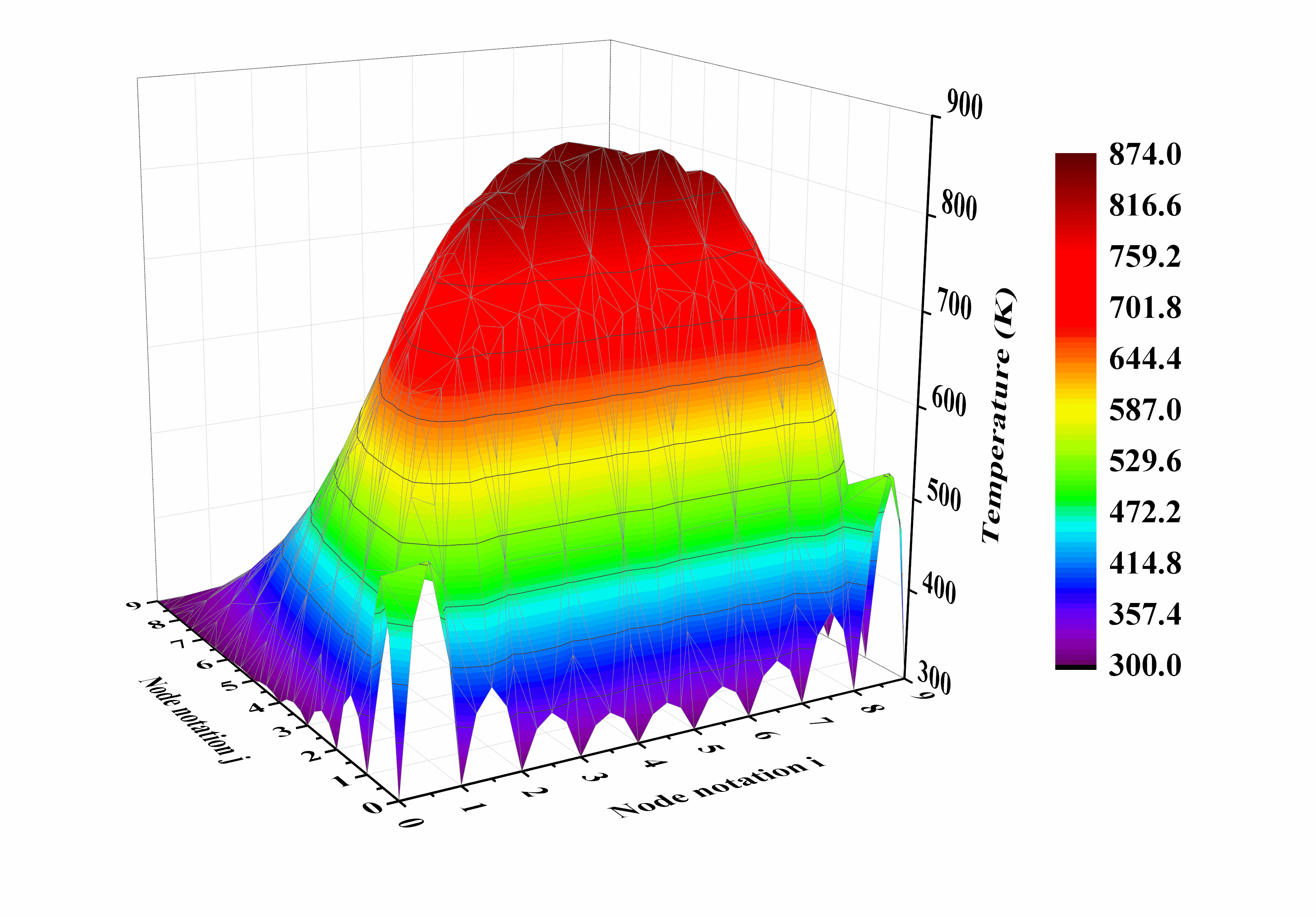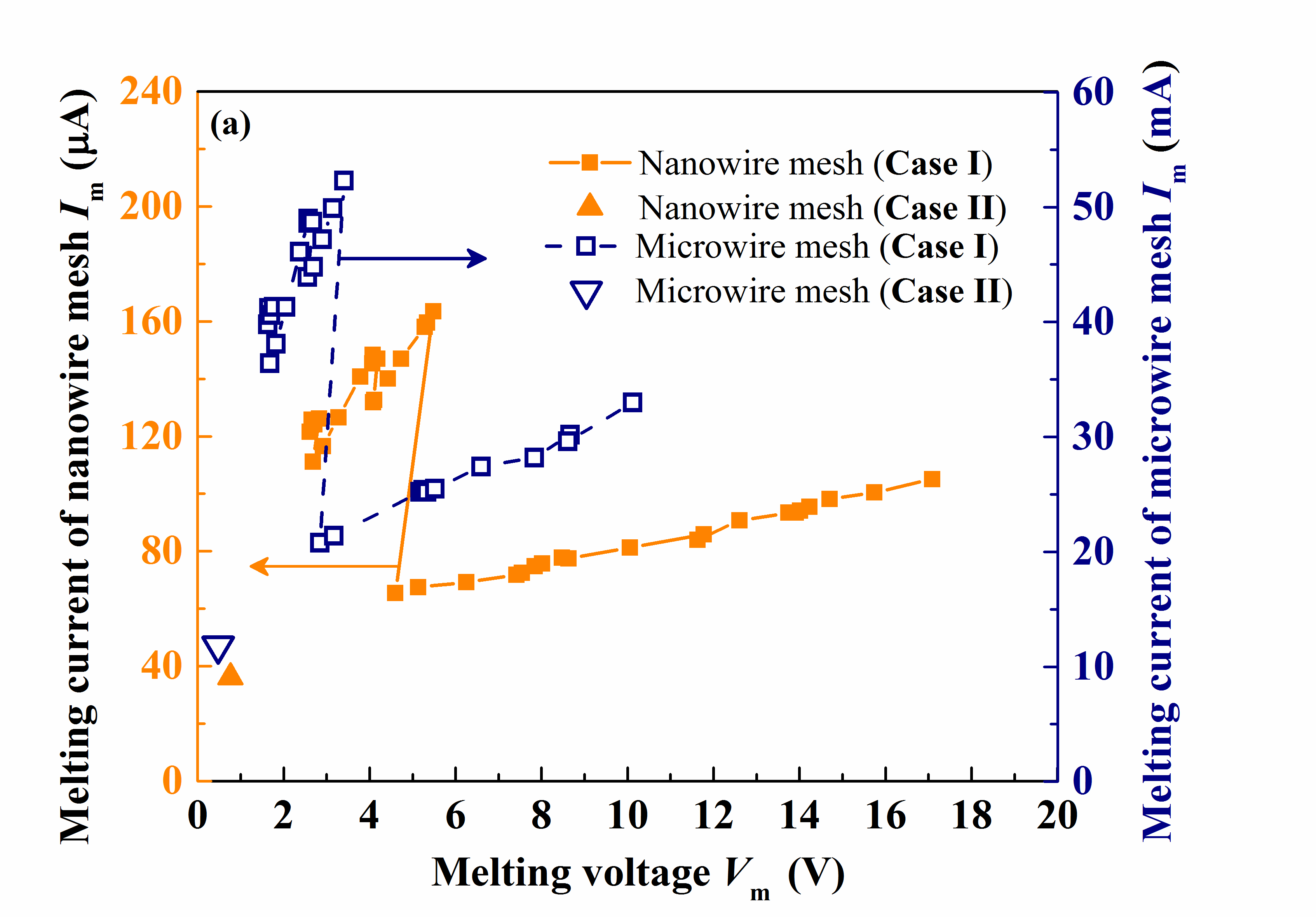薄膜制御による
リチウムイオン電池負極の高性能化に関する研究
リチウムイオン電池負極の高性能化に関する研究
近年、リチウムイオン電池(LIB)は携帯電話やパソコンなどの小型モバイル機器から、飛行機や電気自動車などの大型交通機械まで、幅広く応用されている。これらの機器・機械の高性能化の進展に伴い、LIBの高容量・長寿命化も不可欠となってきている。そこで、現在実用化されている炭素(理論容量:372mAh/g)に比べ格段に高エネルギー密度を有するSn(理論容量:994mAh/g)は、次世代のLIBにおける負極材料の有力候補の一つとして期待されている。
しかし、実際に作動した場合、初期容量は確かに高いが、充放電ならびに熱に伴う急激な体積変化により、サイクル特性の低下につながる電極の崩壊や、電極間の短絡の原因となるSnウィスカの発生という重大な問題(図1)がある。これらの問題を解決するために、他金属との合金化や酸化物材料の適用等、様々な手法が試みられているが、難題ゆえに未だに十分な特性が得られていない。
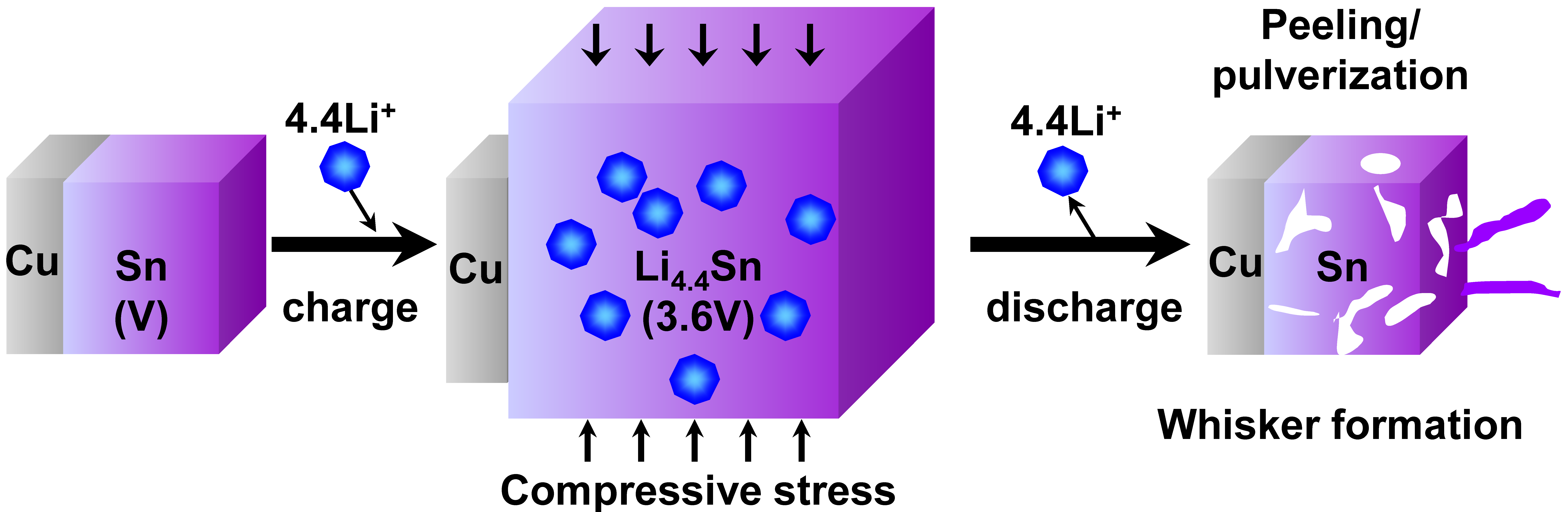
そのため、LIBの高容量化と長寿命化の両立を図るために、成膜条件を調製することで薄膜構造を意図的に制御することを提案し、充放電時にLiとの合金化・脱合金化に伴う急激な体積変化に起因した破壊を緩和することにより、Sn薄膜負極における充放電特性の向上(図2)に取り組んでいる。
しかし、実際に作動した場合、初期容量は確かに高いが、充放電ならびに熱に伴う急激な体積変化により、サイクル特性の低下につながる電極の崩壊や、電極間の短絡の原因となるSnウィスカの発生という重大な問題(図1)がある。これらの問題を解決するために、他金属との合金化や酸化物材料の適用等、様々な手法が試みられているが、難題ゆえに未だに十分な特性が得られていない。
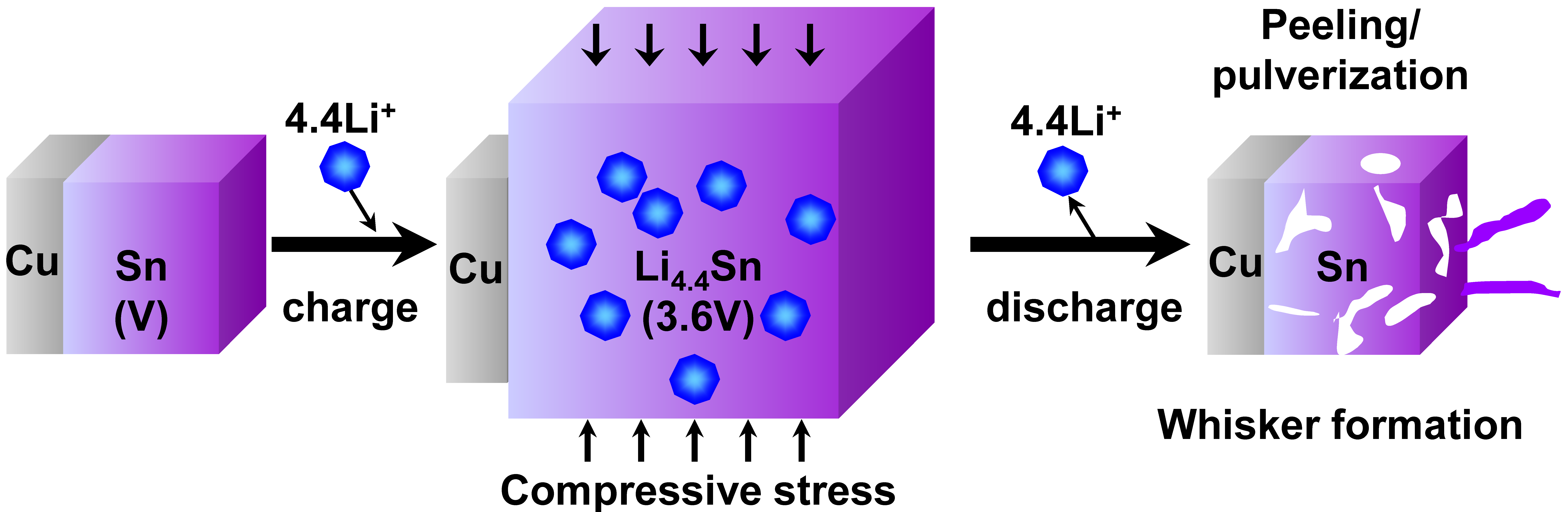
図1 LIB用Sn薄膜負極における破壊
そのため、LIBの高容量化と長寿命化の両立を図るために、成膜条件を調製することで薄膜構造を意図的に制御することを提案し、充放電時にLiとの合金化・脱合金化に伴う急激な体積変化に起因した破壊を緩和することにより、Sn薄膜負極における充放電特性の向上(図2)に取り組んでいる。
金属微細ワイヤメッシュからなる
透明導電膜の信頼性評価に関する研究
透明導電膜の信頼性評価に関する研究
透明導電膜は、可視光域での透明性と導電性という通常相反する性質を併せ持つ薄膜であり、太陽電池やタッチパネル等光電デバイスに欠かせないものである。近年、透明導電膜の主流として実用されている酸化インジウムスズ(ITO)は、原料であるInの資源枯渇が懸念される上に機械強度が弱いため、代替材料の開発が盛んである。その中で、金属微細ワイヤメッシュからなる透明導電膜(透明基板上に規則的もしくはランダムに交差して配置された複数の金属微細ワイヤからなるメッシュ)は導電性・透明性・柔軟性を持つため、注目が集まっている。
しかし通常動作かにおいて薄膜全体に電流が流れるITO透明導電膜に対して、金属微細ワイヤ透明導電膜では、ワイヤ自体が電流通路を担う。このワイヤの断面積は小さいため、透明導電膜全体に微小な電流を流しても、膨大な電流密度が生じる。そこで金属微細ワイヤにおけるジュール発熱が増加し、温度が上昇し、ワイヤ自体が溶断しやすくなり、導電デバイスの劣化もしくは故障につながる。
そして、金属微細ワイヤ透明導電膜の高性能化を目指す創製手法の開発を行うとともに、電気的破壊に係る信頼性の確保に関する研究も取り組んでいる。まず高度解析プログラムを開発し、ジュール熱による温度分布(図1)を可視化し、電気的破壊挙動を予測した。次に金属微細ワイヤならびにワイヤメッシュにおける通電実験を行い、その破壊挙動ならびに諸影響因子(図2)を解明した。さらにこれらに基づき、高信頼な金属微細ワイヤメッシュからなる透明導電膜の開発を行っている。
しかし通常動作かにおいて薄膜全体に電流が流れるITO透明導電膜に対して、金属微細ワイヤ透明導電膜では、ワイヤ自体が電流通路を担う。このワイヤの断面積は小さいため、透明導電膜全体に微小な電流を流しても、膨大な電流密度が生じる。そこで金属微細ワイヤにおけるジュール発熱が増加し、温度が上昇し、ワイヤ自体が溶断しやすくなり、導電デバイスの劣化もしくは故障につながる。
そして、金属微細ワイヤ透明導電膜の高性能化を目指す創製手法の開発を行うとともに、電気的破壊に係る信頼性の確保に関する研究も取り組んでいる。まず高度解析プログラムを開発し、ジュール熱による温度分布(図1)を可視化し、電気的破壊挙動を予測した。次に金属微細ワイヤならびにワイヤメッシュにおける通電実験を行い、その破壊挙動ならびに諸影響因子(図2)を解明した。さらにこれらに基づき、高信頼な金属微細ワイヤメッシュからなる透明導電膜の開発を行っている。
拡散現象を活用した
金属(酸化物)微細材料の創製に関する研究
金属(酸化物)微細材料の創製に関する研究
拡散現象であるストレスマイグレーション、エレクトロマイグレーション、イオンマイグレーションは、異なる駆動力下で原子もしくはイオンが移動することによって、配線内もしくは配線間にはボイドもしくはウィスカなどが形成し、配線の断線や短絡を生じるため、半導体デバイスの故障メカニズムとして知られている。半導体デバイス信頼性の向上を実現するために、これらの拡散現象を抑制する研究が盛んに行われている。
一方、近年拡散現象を活用して金属(酸化物)微細材料の創製に関する研究も進んでいる。現在はイオンマイグレーションを中心として、増速機構の究明と制御手法の開発により、意図的な金属(酸化物)微細材料の創製、特性評価、ならびにガスセンサへの応用に取り組んでいる。
一方、近年拡散現象を活用して金属(酸化物)微細材料の創製に関する研究も進んでいる。現在はイオンマイグレーションを中心として、増速機構の究明と制御手法の開発により、意図的な金属(酸化物)微細材料の創製、特性評価、ならびにガスセンサへの応用に取り組んでいる。