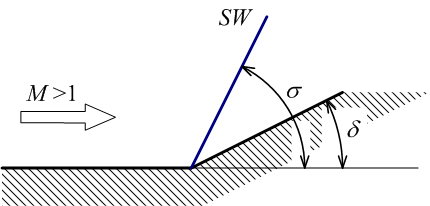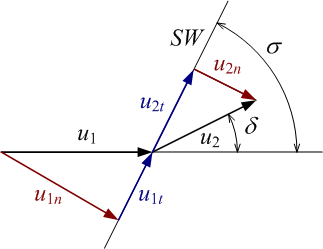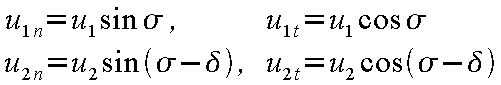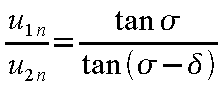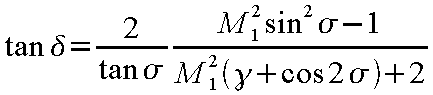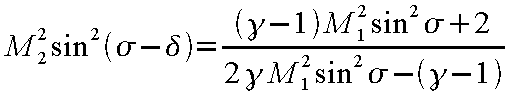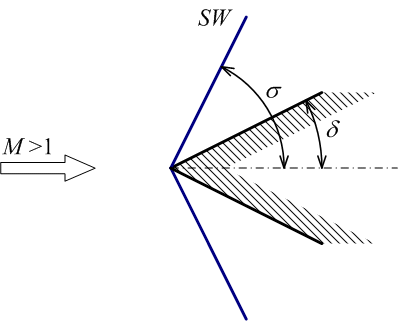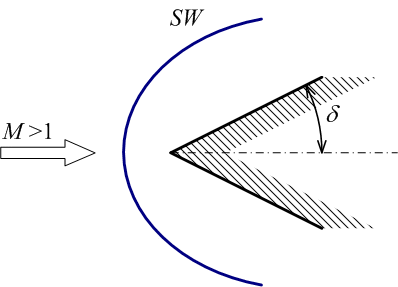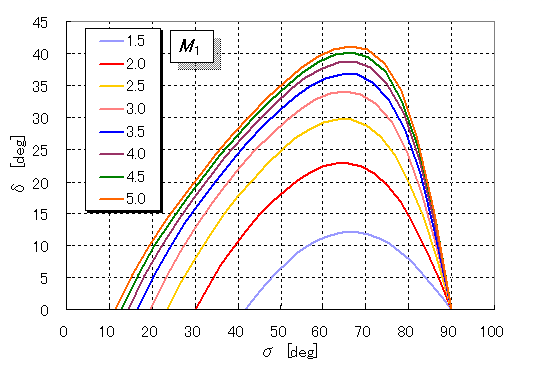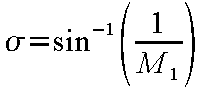|
● 付着衝撃波を利用したマッハ数計測
下図のような半頂角δが既知のくさび型物体を超音速流中に挿入すると、
傾き角σの斜め衝撃波が発生する。この衝撃波は、物体の先端に付着したものであるため
付着衝撃波と呼ばれる。
よって、σを測定することによって式(12-37)から衝撃波発生前の
マッハ数M 1
を求めることができる。ただし、M 1
を算出するにはコンピュータの支援が必要である。
また、同様に式(12-38)から衝撃波発生後のマッハ数M 2
を計算できる。
ここで、δを固定して式(12-37)を考察すると、σが求まるM
1
には下限があることがわかる。
この下限を下回ったM 1
では付着衝撃波となることができず、下図のような
物体から衝撃波が離れた離脱衝撃波となる。
また、同様にM
1
を固定して(パラメータとして)式(12-37)を考察すると、以下のグラフのような曲線が得られる。
図のようにσの上限はM
1
によらず90°であるが、下限はマッハ角と同じ
|
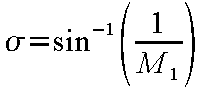 |
|
(12-39) |
|
|
となる。
図より、各マッハ数において、δの最大値であるδmax の存在が確認でき、
このδmax より上の値のもつδではσが求まらないことがわかる。(δ=δmax である場合、M
2 = 1 となる。)
よって、δmax <δである場合、離脱衝撃波となる。また、δmax >δである場合、σは2種類の値を持つ。
δmaxにおけるσをσmとすれば、σ<σmの場合にはM
2 > 1 となり、逆にσ>σmの場合にM
2 <1 となる。
M
2 > 1の場合を弱い衝撃波、M
2 <1の場合を強い衝撃波と呼んでいる。
この弱い・強い衝撃波のうち、どちらが発生するかは上流と下流の圧力に依存する。
一般に、下流/上流の圧力比が小さい方の弱い衝撃波が発生することが多い。
このことからも斜め衝撃波後の流れは超音速であることが多いといえる。
なお、円形のような鈍頭物体の場合にはδが90°であり、
M 1
によらずδmax よりも大きいため常に離脱衝撃波となる。
○ 以下にくさびによるマッハ数測定の計算表示プログラムのリンクを示す。
ファイルには、半頂角δの計算および付着・離脱衝撃波の判定も含まれている。
くさびによるマッハ数測定の計算プログラム[表計算ファイルのダウンロード]
表計算ファイルの各タブで計算を行う。
|