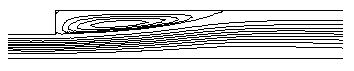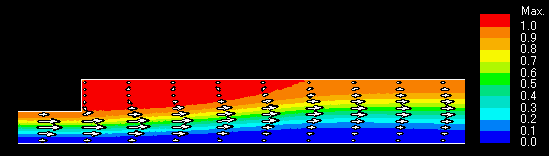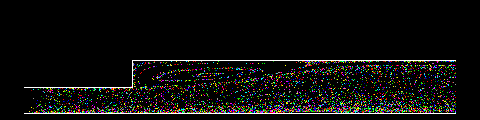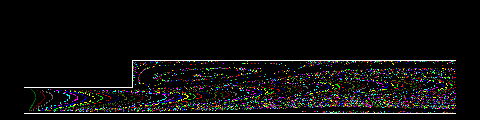| 適切な視覚効果による流れの把握 |
|
はじめに |
||||
|
|
||||
|
従来の画像 |
||||
|
上では、はく離渦内(下図の赤色の部分)を除いた領域(下図の緑色の部分)において流線関数の値を等間隔で描いたものである(はく離渦内の流線間隔はその1/10)。よって、流線関数の性質を知っている場合は、どこで流れが速くなるのかは容易に把握できる。また、定常流であるのでこの流線図だけで十分なのである(各流線についてその値を明示する必要もあるが)。 しかし、これから流体工学を学ぼうとする者や流れ現象に関して興味を持ち理解しようと努めている者にとってはもっとわかりやすい表現法によって流れを観察したほうがよいであろう。その後、流線関数等の性質を理解すればよい。 |
||||
|
カラー画像の例 |
||||
|
|
||||
|
動画の例 |
||||
|
|
||||
|
まとめ |
||||
|
|
||||
|
(Flow Visualizationへ) → 戻る |
(C) 2004 Norifumi Ono
Lab. Simulation Laboratory
Tohoku Gakuin Univ.