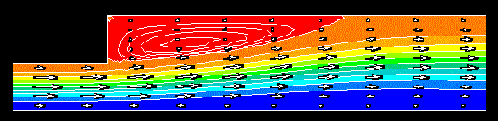|
本研究室におけるコンピュータを利用した流体解析(CFD)の位置づけ
CAE*の側面から
現在、コンピュータを利用した流体解析に関する教科書的文献は、1980年代と比較すると格段に充実しております。これらの書籍は、主に1995年ごろに多数出版され、流体解析の第一段階的手法は完成の域に達したといえます。この点から、大学生や大学院生(修士)のような比較的初学者でも流体解析の初歩を容易に習得できる可能性があり、書籍には解析プログラム(ソースコード)が付属している場合もあります。しかし、解析に必要な環境が十分整っているとはいいがたいのが現状です。これは、解析プログラムの多くがフォートラン言語でかかれていたことや結果表示プログラムまでは付属していないことなどによります。また、プログラムを学ぶ前に解析結果を知ることは学習効率が高いといえます。さらに、当然ではありますが、解析手法は年々高度かつ複雑になってきております。このような観点から、本研究では、世界的に普及している表計算ソフト(マクロ機能)および言語ソフトを使用し、一般座標系非圧縮性および圧縮性流体解析学習ソフトの開発を行っております。このソフトでは、計算結果に基づく等値線や速度ベクトル線などを表示できることはもちろん、格子作成やその格子形状・格子数依存性、収束性なども調べることができます。あわせて、流線関数や圧力分布などの二次元流路内諸量の値や条件よる変化についても学習を可能としております。
本研究室では、このようなソフトウエア構築に関するノウハウを学習環境のみならず、より高度な流体解析ソフトの開発(アルゴリズム開発など)に利用しております。
* "Computer Aided Education" と"Computer
Aided Engineering" の両方の意味を
もたせることができるため本研究室では、CAE
という略語を用いています。
また、一般的なコンピュータ支援教育を示す、CAI
(Computer Assisted Instruction) よりも
高度(大学生向け)であるという意味合いを込めております。
下図は、本研究で開発されたソフトウエアを用いて計算・表示されたステップを過ぎる流れの解析例です。
|
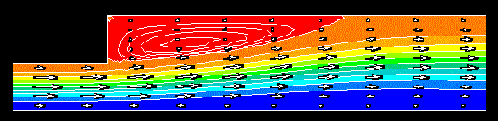
流線と速度ベクトル線図
|
|
|