あとがき
日常会話では精度と確度という言葉を区別せずに使いますが、心理物理学の測定について考える場合はそのような大雑把な使い方の誘惑に負けてはいけません。このウェブサイトの内容を全て学び終えたら、もうそのような気持ちは無くなったと思います。一度その区別がつけば、なぜ両者の区別が難しかったのか不思議に思うでしょう。おそらくその難しさは、精度と確度の概念が統計学的な抽象概念であることに関係しています。すなわち、標準偏差がひとつの数値から算出できないように、ただ一度の判断では精度について何も言うことができないのです。精度と確度は、平均や標準偏差が一連の値を抽象したり要約したものであると同様に、一連の判断を抽象したり要約したものです。要点を繰り返すと、精度は偶然誤差の裏返しであり、確度は恒常誤差の裏返しなのです。それらは一連の判断の二つの独立した側面を表しています。すなわち、ある線分の長さについての一連の判断の精度がわかっても、その確度については何もわかりません。同様に、その確度がわかっても、その精度については何もわからないのです。このサイトの冒頭で定義された心理物理学的変数の用語に置き換えると、JND の大きさがわかってもPOEとPSEの間の差である恒常誤差(CE)はわかりませんし、その逆も同様なのです。独立した概念としての精度と確度を図1に示します。
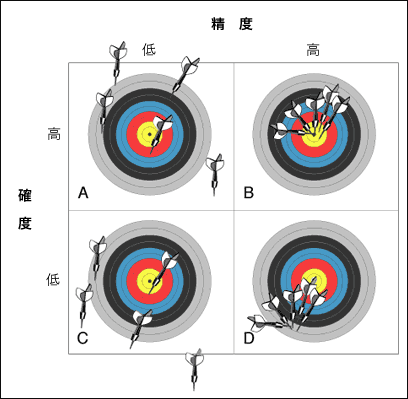
図1. 独立した概念としての精度と確度の図解。それぞれの縦の列(A, CとB, D)は同じ精度で、横の列(A, BとC, D)は同じ確度です。
精度と確度は独立していますから、反応バイアスや実験手続きは一方に影響を与えることなく他方に影響を与えうるのです。例えば、極限法において「等しい」と答えようとする反応バイアスはJNDを大きくしますし、「等しい」と答えようとしないバイアスはJNDを小さくします。これらのバイアスは精度に影響しますが、確度には影響しません。別の例をあげますと、調整法で下降系列のみが用いられた場合、期待誤差があると客観的等価値 (POE)より大きな反応が生じます。こうした手続きは精度に影響を与えることなく確度を低下させ、正の恒常誤差が生じます。この恒常誤差は試行をカウンターバランスさせることで、つまり上昇系列の試行と下降系列の試行を同じ数だけ実施することで取り除くことができます。下降系列でのPSEの変動は上昇系列での変動とは反対方向にずれると思われます。しかしながら、新たに求める一連の判断からこのように恒常誤差を取り除くことは精度を下げることになります。すなわち、この手続きでは期待誤差(あるいは慣れの誤差)が下降系列ではPSEより大きな(小さな)調整結果を、上昇系列においてはPSEより小さな(大きな)調整結果を生み出すのです。
あなたが心理物理学的測定法の実験手続きを選択する場合、精度と確度のどちらに実験の焦点があてられるのかを考慮しなければなりません。例えば、ウェーバーの法則の検証での主な関心は精度でしたから、JNDの測定からバイアスを取り除くことを問題にしなければいけないわけです。この理由から、もし期待誤差か慣れの誤差が生じているなら、調整法で上昇系列と下降系列をカウンターバランスすることは、より大きな偶然誤差を生じさせてしまいます。もし期待誤差か慣れの誤差が大きい場合、これらの誤差とは無縁の恒常法を使うことができます。これに対し、ミュラー・リヤー錯視の大きさを測定する場合の主な関心は、確度あるいは確度の欠如でした。その目的は、手続きや反応のバイアスから生じるどのような恒常誤差も含まずに、矢羽根の向きによる恒常誤差を測定することでした。この場合、カウンターバランスすることは、期待誤差か慣れの誤差のどちらかによるPSEのバイアスを取り除くでしょう。こうした点をよく知る実験者なら、上半視野に提示される刺激の傾向が下半視野に提示される刺激のそれと同等になるようコントロールするため、標準刺激の位置の上下もカウンターバランスするでしょう。要約すると、実験者にとって大切なことは(a)測定されているのは何なのか、精度なのか確度なのかをはっきりさせること、そして(b)測定されるもののデータを汚しうるバイアスの元を取り除くこと、なのです。
理論的には、主観的等価値(PSE)、丁度可知差異(JND)、不確定帯(IU)、そして上弁別閾(UT)と下弁別閾(LT)の値は、それぞれの測定法では異なる順番で求められますが、3種類の測定法全てで同じになるはずです(図2参照)。極限法では、UTとLTが最初に決められ、それからIU、PSE、そしてJNDが求められました。恒常法では、UT、PSE、そしてLTが最初に決められて、それからIUとJNDが求められました。調整法では、PSEとJNDが最初に算出され、それからIU、UT、そしてLTが求められました。しかしながら、おそらくあなたが例題実験の1を行なってわかったように、実際には異なる方法で求められたそれらの値は同じになることはあまりありません。それぞれの方法は原因の異なるバイアスと誤差の影響を受けるので、異なる値が得られることになるのです。(反応バイアスや我々の判断に影響を与える要因についてもっと知りたい場合は、このリンクの最後で引用されている信号検出理論を勉強してください。)
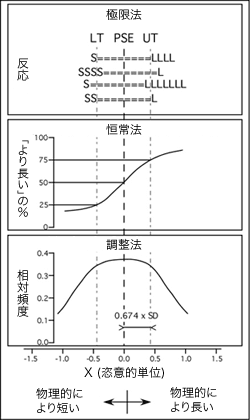
図2.3種類の測定法で得られた心理物理学的変数の理論的に等しい値の図解。2番目と3番目のパネルのカーブの両端はその関数の関連する部分を拡大するために切り落とされている。
どの方法が最も優れているのでしょうか。どの方法にも長所と短所がありますから、あらゆる状況で最良の唯一の方法は無いのです。極限法は最も時間がかかりません。恒常法は反応バイアスの影響を最も受けにくい方法ですが、より多くの試行数が必要です。それに加えて、この方法で用いる適切な比較刺激を選ぶには予備実験が必要になります。調整法には実験者が比較刺激を選ぶ必要がないという長所があります。どの方法が最良かは、どの心理物理学的変数をあなたは取り上げるのかということと、時間の制約という要因に依存します。
心理物理学的測定の導入教育として、このサイトは不完全です。というのは、絶対閾をどのように測定するかも、より新しい測定法についても触れていないからです。既に述べた3種類の測定法は絶対閾、すなわち提示回数の50 %が検出される刺激値の測定にも使えます。絶対閾付近の刺激値は別な装置が無いと制御が困難なので、このパッケージでは絶対閾の測定法を説明しませんでした。しかしこのサイトを一通りやり終えると、絶対閾の測定法を理解しやすくなります。閾値を測定するより新しい方法は、極限法の変形である「階段法」と「PEST」(系列テストによるパラメーター推定)の手続きとして知られています。これらの方法はこのパッケージの範囲を越えているのでここでは取り上げませんが、極限法を理解すればこれらの方法を理解する助けになるでしょう。(さらに詳しく知りたい場合には、このリンクの最後に掲載した参考書のどれかを参照してください。)
心理物理学の問題には長い歴史があり、心理学の他の問題と関係しています。このパッケージの3種の測定法は心理物理の科学(精神物理学)の祖、フェヒナー(1860-1966)が用いたものです。あなたがこのサイトで学習したウェーバーの法則は、物理的刺激の大きさとそれにより引き起こされる心理的経験との間の関係を記述しようとする、フェヒナーの法則として知られるものの礎となりました。臨床心理学における「不安」、社会心理学における「態度」、実験心理学における「JND」のように、心理学のどの領域でも変数の測定が必要です。あなたが何を測定したいにせよ、得られた数値の精度と確度はどうなのかに注意しなければなりません。ミュラー・リヤー錯視のように、不正確さの程度そのものもしばしば関心事になります。この場合には、提示順序のような他の要因ではなく、矢羽根の向きによって引き起こされた不正確さを測定することが目標なのです。そのため、カウンターバランスの技法が用いられました。どの心理学の領域をあなたが学ぶにせよ、このような望まない不正確さを取り除く技法を用いることが求められます。このサイトをやり通して身につけたことが、心理学の全領域と関連する分野で学ぶあなたに、おおいに役立つことを望みます。
精度と確度という用語は使われていませんが、ほとんどの知覚の教科書にはこのサイトで取り上げた概念と方法についての記述があります。おすすめの本を何冊か以下に列挙します。
初級向け文献
Coren, S. & Ward, L.M. (1989). Sensation & perception (3rd Ed.). U.S.A.: Harcourt Brace Jovanovich.
Galanter, E. (1962). “Contemporary psychophysics.” In (T. Newcomb, ed.) New directions in psychology. New York: Holt, Rinehart and Winston.
Goldstein, E.B. (1989). Sensation and perception. (3rd Ed.). Belmont, CA: Wadsworth.
Schiffman, H.R. (1990). Sensation and perception: An integrated approach (3rd Ed.). U.S.A.: John Wiley & Sons.
Sekuler, R. & Blake, R. (1990). Perception (2nd Ed.). U.S.A.: McGraw-Hill.
石口彰 (2006). キーワード心理学シリーズ 視覚 新曜社
上級向け文献
Baird, J. C. (1997). Sensation and Judgment: complementarity theory of psychophysics. Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, NJ.
Farell, B. & Pelli, D. G. (1998) Psychophysical methods, or how to measure a threshold, and why. In R. H. S. Carpenter & J. G. Robson (Eds.), Vision Research (pp. 129-136). New York: Oxford University Press.
Fechner, G. T. (1860/1966). Elements of Psychophysics, Vol. 1. Translated by H. E. Adler. New York: Holt, Rinehart and Winston.
Gescheider, G. A. (1997). Psychophysics: the fundamentals. (3rd ed.) Lawrence Erlbaum Associates, Mahwah, NJ. (ゲシャイダー,G. A. 宮岡徹(監訳)(2002, 2003).心理物理学—方法・理論・応用(上・下) 北大路書房)
Macmillan, N. A. & Creelman, C. D. (2005) Detection theory (2nd edition). Mahwah, New Jersey: Lawrence Erlbaum
坂田勝亮 (1991). 知覚研究における測定 市川伸一(編著) 心理測定法への招待 —測定からみた心理学入門— 新心理学ライブラリ13 梅本尭夫・大山正(監修) サイエンス社 pp. 149-188.