実験を実施する
学生ユーザーの皆さんは心理物理学の実験を実施した経験が無いでしょうから、サブメニューの実験とデータ分析を以下のように作り込みました。このリンクをクリックすると、あなたがメニューから選んだのがどのトピックでも、実験を計画することが可能です。プログラムのデータ分析の部分では、あなたが計画して実施する実験で取得したデータを分析します。チュートリアルとは違い、ここでは答えなければならないクイズ項目はありません。データは表とグラフの両方に表示され、チュートリアルと同様に、分析の解説を見ることができます。
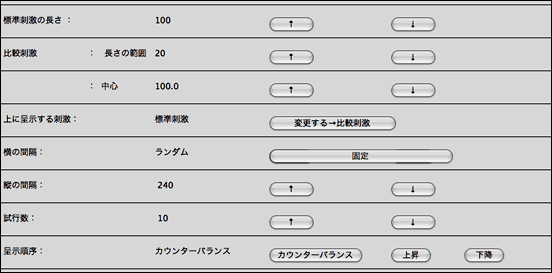
図1.極限法で実験とデータ分析を選んだ場合の初期画面
以下は「実験とデータ分析」で操作可能な別々の変数についての説明です。
精度と確度を測定する
それぞれの測定法で、図1に示す初期画面か類似の画面が表示され、以下の実験変数のひとつかそれ以上を変化させた場合の効果を特定するよう、実験を計画できます。
標準刺激の長さ:標準刺激の長さはチュートリアルで100スクリーンユニットにセットされています。この標準刺激を30から380スクリーンユニットの間で変化させることができます。
比較刺激:極限法と恒常法では、比較刺激の値の範囲とその範囲の中央点の値を変化させることができます。使える範囲は10、20、30、40、50、60、70、そして80スクリーンユニットです。使用可能な中央点は21から416スクリーンユニットです。チュートリアルでは、その範囲は20ユニットであり、中央点は100ユニットです。等間隔に割り振った比較刺激が極限法では21個、恒常法では11個ありますから、範囲を20ユニットにすると一番近い比較刺激同士の差は極限法では1ユニット、恒常法では2ユニットになります。もしあなたが別な範囲を選択すると、その差は自動的に比例配分されて変化します。たとえば、範囲を40ユニットにすると、その差は極限法では2ユニット、恒常法では4ユニットになります。選択される範囲はIUよりも大きくなければいけませんし、一番近い比較刺激同士の差はJNDよりも小さくなければなりません。小さい標準刺激に対しては範囲を狭くし、より大きな標準刺激に対しては範囲をより広くする必要があります。(こうしなければならない理由はあなたがウェーバーの法則を学んだときに明らかになるはずです。)中央点は標準刺激(POE)を変えると自動的に変化しますが、PSEとPOEが違うと考えられる場合は、範囲の中央点をPOEとは異なる値にしたいかもしれません。調整法では、その範囲は自動的に標準刺激の20パーセントに設定され、中央点はPOEに設定されます。例えば、標準刺激が100ユニットならばその範囲は90から110ユニットに設定されます。
上に呈示する刺激:上に呈示する刺激を、標準刺激と比較刺激のどちらにも設定できます。チュートリアルでは標準刺激になっています。
横の間隔:チュートリアルでの標準刺激と比較刺激は画面上のランダムな位置に出てきますが(互いの水平方向の間隔で)、自分の実験では横方向の位置を固定して線分を呈示するよう選択できます。標準刺激と比較刺激は画面上のランダムな位置に表示されるよう設定されていますが、表示位置を固定したい場合は、「固定」のボタンをクリックして下さい。それから希望する固定位置の間隔を選んでください。間隔は標準刺激の長さによって0から270スクリーンユニットの間で変えられます。間隔を0にすると、標準刺激が比較刺激の真上か真下に表示されます。
縦の間隔:標準刺激と比較刺激の垂直方向の間隔は20から340スクリーンユニットの間で変えられます。
試行数:試行数は極限法では5から50の間で、恒常法では40から150の間で、そして調整法では10から100の間で変えられます。
呈示順序または出発点:下降系列のみ、上昇系列のみ、あるいは上昇系列と下降系列をカウンターバランスしたもののいずれかを選択できます。このオプションは恒常法では利用できません。
精度あるいは確度
このサイトではウェーバーの法則とミュラー・リヤー錯視の実験で調整法が使われています。そのため、表示される初期画面は調整法の初期画面と似ていますし、コンピューターが比較刺激の範囲と中央点を選びます。調整法で行なったのと同様に、上に呈示する刺激、横の間隔、試行数、そして出発点の変数を操作できます。調整法の実験とは異なり、刺激の数は2から7までしか変えられません。ミュラー・リヤー錯視の実験でも調整法のメニューとよく似たメニューが表示されますが、横の間隔は0から200スクリーンユニットの間で、また縦の間隔は20から340の間で変化させることになります。
考えられる実験
以下は試してもらいたい、いくつかの実験です。できれば独自の実験も構築してみてください。なぜなら、実験を計画するという創造的な作業はその計画を実行するのと同じくらい価値があるからです。
実験の変数に異なる値を選択することで、その問題をより深く学ぶことができます。別々なセクションで試行数を変えると、試行数の関数として得られるJND、PSE、ウェーバー比、あるいはミュラー・リヤー錯視量の安定性について学べます。また、極限法と恒常法のところでは、大きな標準刺激に対して比較刺激の値の範囲を狭くすると、これらの測定法の特徴を学べます。用意された比較刺激のセットが標準刺激に対して不適切だと、JNDを測定できないことがわかるでしょう。このような経験は、これらの方法で光量や重量のような線分の長さ以外の刺激のJNDとPSEを測定する時に、比較刺激を選ぶにあたって何を考慮しなければならないかを教えてくれます。
各話題をより深く学ぶ外に、独自の実験を計画することも経験できます。ある実験では、JND、ウェーバー比、あるいはミュラー・リヤー錯視量の変化を見出すため、標準刺激と比較刺激の横と縦の間隔を系統的に変化させてもよいのです。比較刺激の横の配置をランダムにしなかったり、標準刺激と比較刺激をより近くに配置したりすると、被験者はより安易な判断方略を作り上げ、その結果、JNDの大きさと錯視量が小さくなります。このような条件下ではウェーバーの法則は成り立たないといわれており(Weber, 1849)、このことを発見する実験を自分で計画できるのです。
実験はメニューの変数操作に留まる必要はありません。三種の心理物理学的測定法をそれぞれ他の測定法と比較することが可能です。(メニューの一番下の方にある例題実験の実験Iを参照。)あるいは、ミュラー・リヤー錯視において線分の長さを変える効果を検証したいかもしれません。(例題実験の実験IIを参照。)
「実験とデータ分析」は外部の条件操作と共に利用することが可能です。眼鏡(またはコンタクトレンズ)をした観察者は、同じ人が眼鏡(またはコンタクトレンズ)を外した場合よりJNDが小さくなるだろうという仮説を立てることもできます。観察者には、一度は眼鏡(またはコンタクトレンズ)をして、もう一度は眼鏡なしでという具合に、二度実験してもらってよいでしょう。観察者間で、実験の順番をカウンターバランスすることを忘れないで下さい。コンピュータ画面にマスキングテープを貼り、ポンゾ錯視量を測定することもできます。(例題実験の実験IIIを参照。)標準刺激として垂直と水平の線分を描いた紙を貼り付けて、水平垂直錯視を測定するのはどうでしょうか?